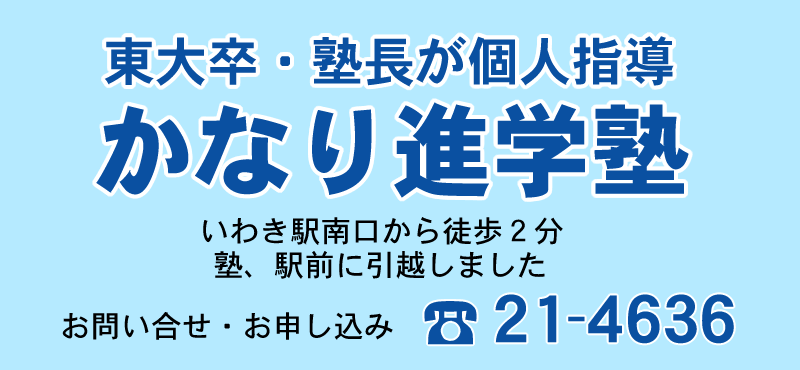 |
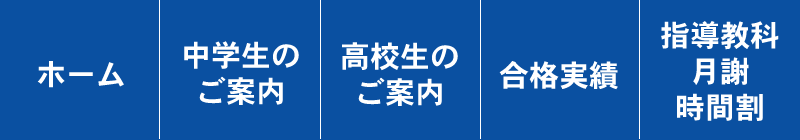 |
| 高校生ワンポイント |
| バックナンバー 2025.7月分 2025.6月分 2025.5月分 2025.4月分 |
| 6月 その1>> <高校生ワンポイント> 高3女子・母> 部活の大会はまだ先です <質問> 陸上部とか日程が早いですよね。 他の部活も、6月には地区大会があります。 娘は吹奏楽部なので、逆に遅くて。 最初の地区大会は7月。 その後、県そして東北と続いて。 最後の東日本まで行ってしまうと、なんと10月になってしまいます。 娘の高校は、昨年、東北で4位。 東日本大会には3校出場できるので、あと一歩でした。 というわけで娘たちは燃えています。 が、受験のことを考えると、親としては「ちょっと待って」とストップをかけたくなります。 ・・・ 彼女は英語好き。 部活の練習の合間を縫って、英検にチャレンジ。 運良く2級に合格できました。 いずれ準1級にもチャレンジしたい、とのこと。 塾長は「私立・専願の人は推薦入試から」と言ってますよね。 先ほどの日程で、推薦入試に間に合いますか? <回答> 推薦入試について> 総合型は10月にテストがあります。 ということは、夏くらいから準備をしないと間に合わない。 2か月の準備期間はほしいですから。 とすると、勝ち進んだ場合、総合型を受けるのは間に合わないかな。 ・・・ 次に公募推薦入試。 こちらは11月とか12月になります。 なので、ギリギリ間に合うでしょう。 どんな大学に、どんな日程で公募推薦入試があるか。 テストの内容はどんなものか。 今から調べておくとよいです。 ・・・ オープンキャンパス> 推薦入試に面接がある場合、これに出ておくのは必須。 夏休みが良いタイミングです。 部活の練習もあって大変でしょうが、2・3校はぜひ見てきてください。 |
| 6月 その2>> <高校生ワンポイント> 高1女子A> 数学ついていけます <事例> Aさんはこの春、希望していたB高に合格。 A高もなんとか合格できるレベルにはいたのですが。 「入学後、下位で苦戦するよりは」とB高を選択。 上位を目指してがんばっている。 先まで見通せるAさんですから、数学の予習も入学前に着々と進めていました。 数学は苦手科目。 なので、よりいっそう準備に怠りはなかった。 結果、授業は猛スピードで進んでいますが、余裕を持ってついていってます。 他方、中学の時は数学が得意だった友人。 まるで予習してなくて、すでにアップアップ。 準備の差は大きいようです。 Aさんは国立大を目指しています。 英語や国語は得意。 数学がこの調子でいってくれれば、とのこと。 <分析> やりますね、Aさん。 高校で伸びていくのは、こういうタイプの方なんでしょうね。 逆に、中学の時はAさんより成績上位。 学年3番から下がったことがない。 当然のようにA高に合格。 そういう方が、意外と高校で伸び悩むのです。 中学の時に、能力を出し尽くしてしまうのかもしれませんね。 国立大タイプ> 読んでみて、Aさんは国立大タイプだなと感じました。 きちんと準備を進め、いろんな科目を満遍なくこなしている。 国立大の入試には5教科7科目が必要です。 それをこなせるのは、やはりこういう方なんですよね。 突き抜ける> 英語か国語、どちらかが突き抜けるくらい伸びると、さらに良いですね。 学年でもトップを争うくらいに。 するとね、国立大・上位校が見えてくるんですよ。 筑波大や千葉大といった。 ぜひ、そこを目指してください。 |
| 6月 その3>> <高校生ワンポイント> 高2男子B> 数学をやり過ぎる <事例> Bくんは理系。 数学が得意。 将来は国立大、できれば上位校に進みたい。 Bくんの高校は課題が多い。 5月の連休など、何センチ!! という厚さの課題が出た。 なかでも多いのが数学。 その中でもよく出されるのが模試の過去問。 時間がかかる問題が多い。 とはいえ数学が好きなBくんは、それに正面から取り組んでしまう。 解けると、けっこう面白いという。 ただ弊害もある。 他の科目を勉強する時間がなくなってしまうのだ。 とりわけ英語。 2年生になってそれに気づいたBくん。 少しずつ英語の勉強時間を増やした。 すると徐々に成績も伸び始めた。 が、気づくといつの間にか数学を勉強していて。 英語は後回しになる。 せっかく伸びてきた英語の芽。 摘んでしまわないか不安がある。 <分析> 読んでいて、つい笑えました。 なんかね、高校生の時の自分を見ているようで。 「私もこんなだったよなぁ」 懐かしく思い出しました。 ・・・ さて、対処法。 数学が好きなら、そのまま突っ走るといいですよ。 それが将来を切り開いてくれますから。 ただね、勉強する教材は選んだほうがよいです。 アレコレ手を出すのは不可。 あと栄養価が低い教材も不可。 「栄養価が低い」というのは、勉強してもあまり点数が伸びないということです。 模試の過去問がその典型例。 逆に「栄養価が高い」ものとは、一冊の本になっているもの。 これは手間暇かけただけあって、よく出来ています。 おすすめ本: 黄チャート(数研出版) 理系なら、これだけで1A・2B・3Cと厚い本が3冊もあります。 ですから、さらにやる所をしぼる。 「基本例題」が一番のおすすめ。 これを2周3周して暗記してしまう。 これが効率のよい勉強法だと思います。 |
| 6月 その4>> <高校生ワンポイント> 高3男子C> セカンド・ベスト <事例> Cくんは工学部志望。 できれば国立大に行きたい。 成績は良い。 学年で10番くらい。 ただ、彼の高校だと3番以内にいないと、国立大に現役で受かるのは難しい。 あとひと息だが、上位の壁はなかなか厚い。 それと受験科目。 国立大だと5教科7科目と数が多い。 Cくんは器用なタイプではない。 これと決めた科目に集中し、コツコツ続けていくと成果が出る。 だから、科目数が少ないと、そのやり方でも良い結果が出る。 が、国立大のように科目数が多いと、ちょっとキツイ。 そこで私は「県立大もあるよ」とすすめてみた。 こちらだと受験科目が少なくてすむ。 <分析> すすめたときのCくんの印象: どこかホッとしていました。 やはり彼自身も、5教科7科目をこなして国立大に合格するのは、負担になっていたようです。 勉強面でも、心理面でも。 その時、セカンドベストという考え方も紹介しました。 高校生の皆さんは「第一志望」という考え方にとらわれています。 それは塾や予備校のマーケティング戦略によるところも大きい。 たとえてみると、「第一志望・絶対合格」というCMを大量に流されているような状況です。 でも、セカンドベストという考え方もあって。 第一志望がベストだとするなら、それにちょっと足りない。 でも、まあまあ満足。 そういう選択肢がセカンドベストです。 Cくんにとって国立大というのはベストな選択肢。 でも、その代償として負担が大き過ぎるなら、県立大というセカンドベストな選択肢もある。 負担は小さくてすむし。 さてCくん、どうする? |
| Copyright (C) 2004-24 Kanari-Shingakujyuku. All Rights Reserved. |